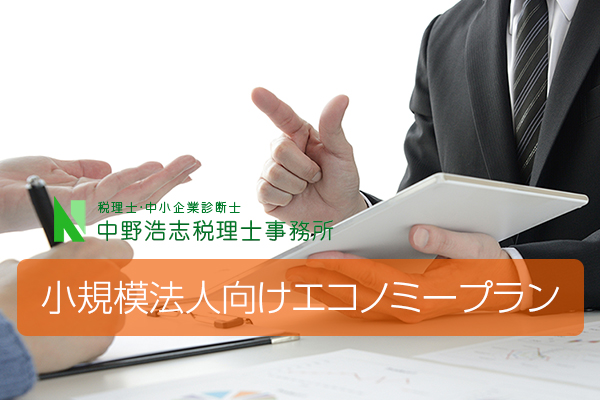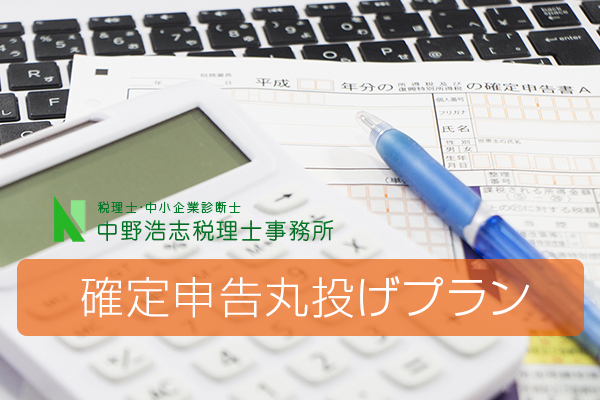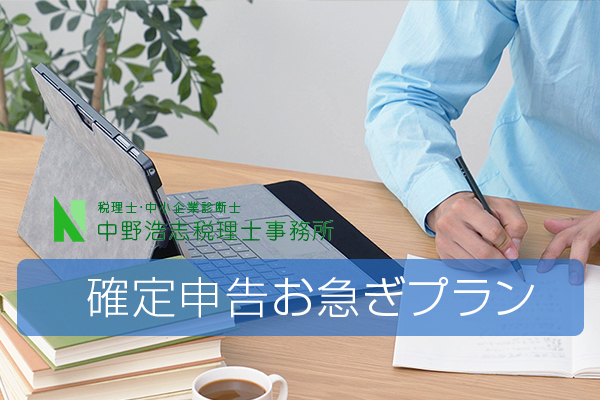法人が損金計上できる福利厚生費の範囲
最近関与先から受けた質問の中で、「従業員の福利厚生を目的として、従業員が施術を受ける整体について当社がその費用の一部を負担したいと考えているが、この負担額は法人の損金として認められるのか?」という内容があった。政府においても賃上げ(令和6年4月13日付け記事「賃上げ促進税制の概要と留意点」を参照)や人材育成に係る税制の拡充を図っている中にあって、企業側にあっても従業員の定着率向上やその待遇改善に向けた取り組みを進めていくことは、今後益々重要になってくるものと考えられ、それに伴ってこうした福利厚生に関する質問も増加することが予想される。
さて、本質問に対して法令上ピンポイントで触れている箇所はないが、例えばレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食・旅行・演芸会・運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、一定の場合を除いて課税しなくて差し支えないとされている。昭和の時代と比べるとかなり下火となった社内旅行や忘年会といった行事については、最近復活の兆しがあるとも言われており、こうした行事の積極的な実施を通じて従業員の福利厚生の向上と節税の双方を実現させていくことは可能であろう。
なお、社内旅行の場合において、自己の都合による不参加者に対して金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされるので、この点は注意が必要である。ちなみに私が初めてこの通達を目にした際にはなかなか厳しい取扱いであると感じた記憶があるが、これについては仮に給与課税しなかった場合の弊害を考えれば納得できる。
話を戻して質問の件については、その実態に基づき個別に判断することになるが、例えば①従業員の福利厚生目的として適切に実施されているか、②全従業員を対象とした制度であるか、③法人が支払を行うか、④社会通念上不相当に高額ではないか、といった点が可否のポイントになると考えられる。この中で特に留意すべき事項は②であり、例えば役員のみなど対象者が限定されている場合には、当該役員に対する給与として課税されるので注意が必要である。ちなみに、食事や住宅の支給については、従業員の負担割合や負担額等について定められていることから(令和4年3月23日付け記事「法人が支給する給与の範囲」を参照)、その認められた範囲内で適切に対応していく必要がある。
最後に、法人の税務は近年益々複雑化しており、これまで以上に正確な処理が求められる。当所では法人向け業務プランとして「顧問契約プラン」、「小規模法人向けエコノミープラン」などによりそのサポートを行っているので、ご関心の向きは是非ご連絡いただきたい。