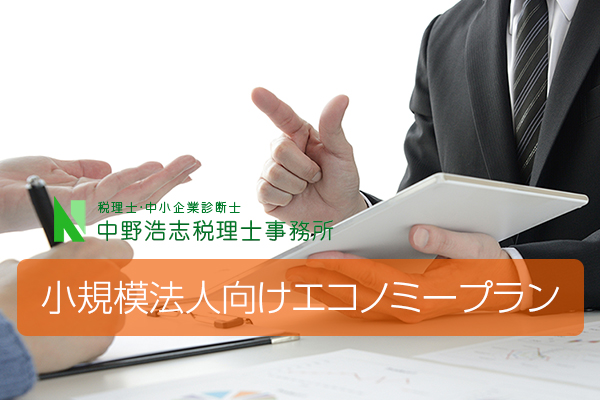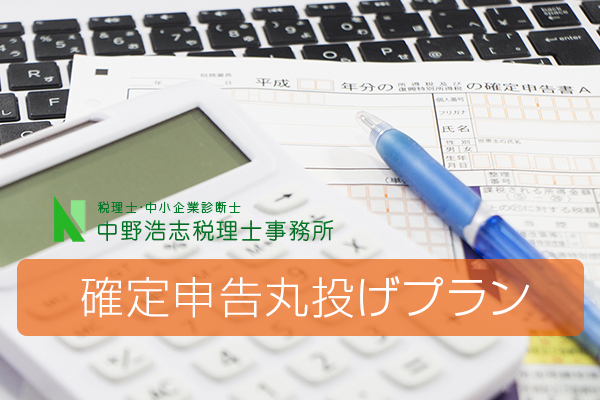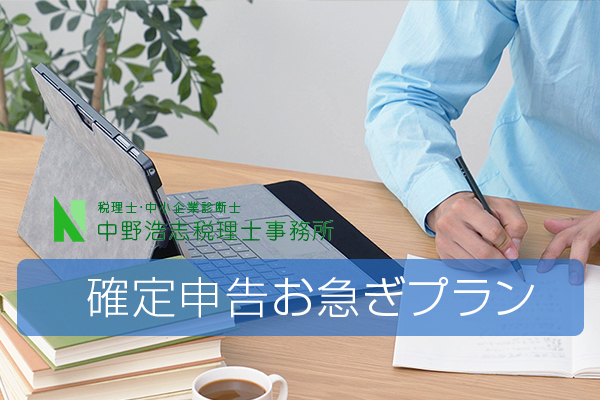令和7年分の年末調整に関する留意事項
今年も残すところ2か月を切り、例年通り年末調整の準備を開始する時期に差し掛かっているが、今年は様々な改正が適用されるため、これまで以上に慎重な事務処理が求められる。そこで今回は、それらの中の幾つかの改正点に絞ってその概要を紹介したい。
まず年初から話題になっていた基礎控除の見直しが挙げられる。具体的には合計所得金額が2,350万円以下の場合には、その金額に応じて基礎控除額が58万円~95万円に引き上げられたため、ほとんどの方が減税の恩恵を受けることができる。但し、最大額である95万円の控除の適用は合計所得金額が132万円以下の納税者に限られることに加えて、住民税の取扱いについては変更がないため、その減税効果は大きく制限されることになる。
次に給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられている。但し、上記の基礎控除額の改正のように給与所得金額に応じて給与所得控除額が増額される仕組みではないため、例えば比較的短時間のパート・アルバイトとして勤務して年収が190万円以下の場合には一定の減税効果を享受することができるものの、年収190万円超の納税者には影響しない。ちなみに、この65万円に上記の基礎控除の最大額(95万円)を加算した合計額が160万円であることから、一般的には160万円の壁と言われている。しかし給与収入が160万円以下であっても、住民税については課税される可能性がある点には注意が必要である。
さらに、大学生や専門学校生の就業調整対策等の観点から特定親族特別控除が創設され、居住者が特定親族(居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(一定の者を除く)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいう)を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除できることとなった。ちなみにこの改正に対応して、社会保険の壁についても扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満の場合(被保険者の配偶者を除く)には、被扶養者認定における年間収入要件が現行の130万円未満から150万円未満に変更されている。
以上、冒頭でも触れた通り今回の改正内容は非常に複雑であるため、特に税務ソフトを利用せずに手計算で従業員の年末調整を行っている事業所については、正しい控除額を適用するよう十分な注意が必要である。なお、詳細は国税庁のホームページを参照。