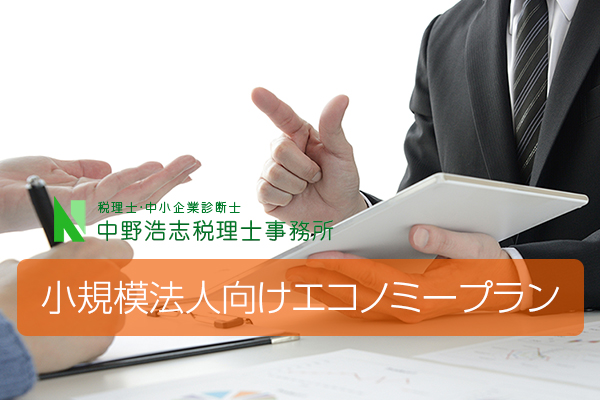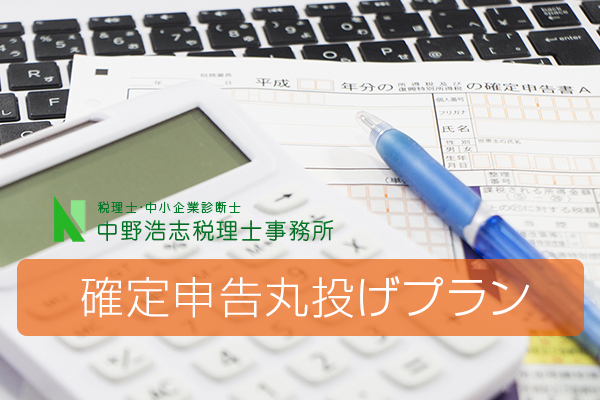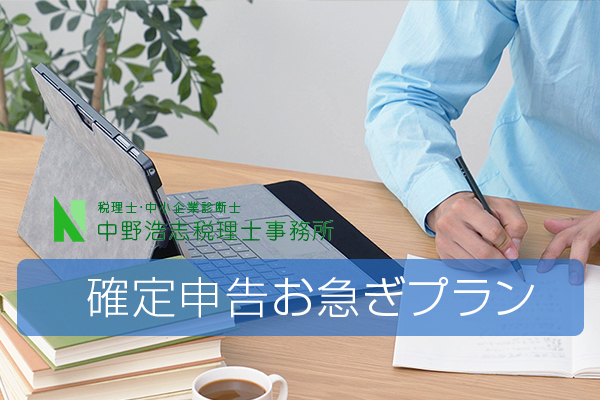諸外国との比較から我が国の消費税率について考える
本日(7月3日)第27回参議院議員選挙の公示日を迎え、これに先立って各党が次々と選挙公約を発表している。その中で今回最も注目すべき点の一つが、生活者支援に向けた具体的な方策について減税又は給付のどちらの方法(又は両方)で行うのかという点である。給付に関しては、既に自民党より原則1人当たり2万円(一定の場合には4万円)を給付する旨が示されている一方、減税に関しては野党各党より消費税率の引下げ又は廃止といった内容が盛り込まれており、選挙の結果次第ではこの消費減税が現実味を帯びてくる。
我が国に消費税が導入された平成元年の税率は3%であったが、その後5%→8%と上昇して現在は原則10%(軽減税率対象品目は8%)である。この税率の妥当性については見解が分かれるところであるが、一つの見方として海外諸国との比較が挙げられ、国税庁のホームページでは諸外国の消費税(付加価値税)の標準税率が掲載されている。これによるとヨーロッパ諸国の標準税率は20%以上というケースが多い。私が約2年前に旅した北欧諸国の税率は25%であったと記憶しており、レストランが発行するレシートにも付加価値税の金額が区分記載されていた。これらの国々は一定の医療費や教育費が無料であることや、老後の生活保障や就業支援の仕組みが充実しており、これらを実現させるための財源が必要であるという点を考えれば順当なところであろう。ちなみに所得税率も日本と比べるとかなり高い税率のようであり、特に低所得者層にとってはかなり厳しいのではないかと思えるシステムである。なお、直近では先月渡航したモロッコがやはり20%(現地の観光ガイドからの情報であるため公式データではない)とのことであり、そのガイドが「モロッコの税率は高過ぎて生活が大変である」と言っていたことが記憶に残っている。
税率に関しては、各国を取り巻く様々な要素を総合的に検討・判断した上で決められており、加えて生活必需品については標準税率ではなく軽減税率が適用されているケースも多いので単純比較は適切ではないが、仮にこの標準税率のみをもって比較すると10%は決して高い税率ではない。一方、アジア諸国の税率は日本と同様に約10%という国が多いことから、少なくともアジア域内で比較した場合には妥当な税率と見ることができ、併せてこの標準税率に関しては概ね西高東低である点も興味深い。従って、税理士事務所の業務負担は更に増えてしまうものの、例えば標準税率に関しては据え置く一方、一定の品目について税率を引き下げるといった対応も十分考えられるだろう。いずれにしても、こうした貴重な税収がどのように使われ、我々の生活に役立っているのかという点こそが最も重要であり、こうした観点も踏まえて我が国にとって適正な税率を考えていく必要があるだろう。
最後に、最近海外を旅する際にはできる限り現地の方(観光ガイドやホテル従業員など)から税金や社会保険に関する話を聞くようにしており、その中にはこれまで知り得なかった興味深い話も数多くあるので、こうした機会や経験を通じて専門家として更に見識を深めることができればと考えている。なお、我が国の消費税の創設から現在に至るまでの歴史については、国税庁のホームページを参照。