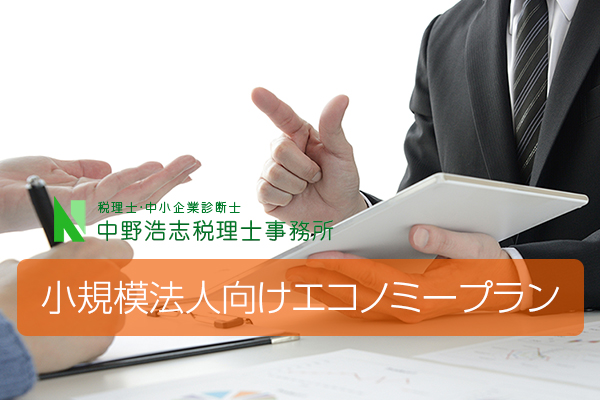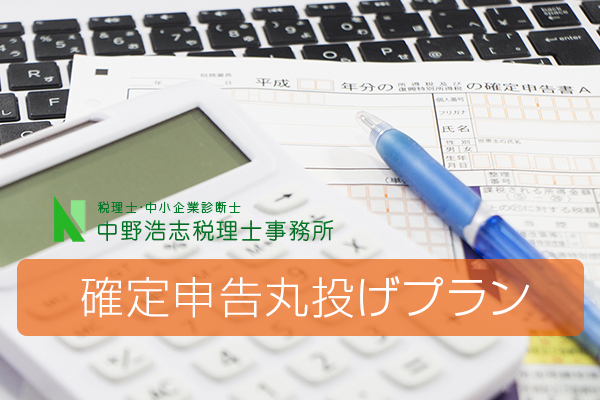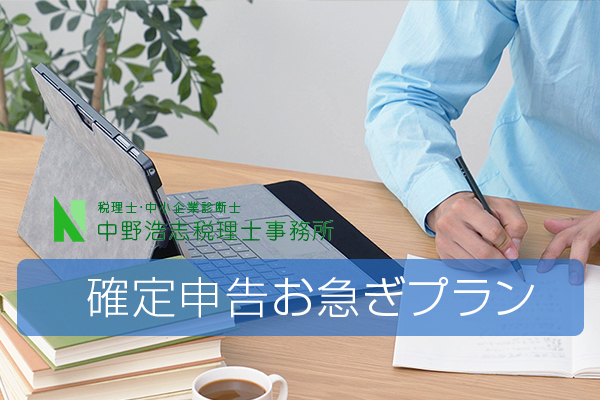総務省がふるさと納税のポイント還元を廃止
納税者が自身の故郷や応援したい自治体に対して税金を納めることができる「ふるさと納税」の利用者は年々増加しており、令和5年度のふるさと納税の全国の受入れ件数は約5900万件、受入額は1兆円を超え、現在地方にとって貴重な財源になっている。その制度概要や利用時の留意点などに関しては、これまで何回か(令和5年12月25日付け記事「ふるさと納税を実施して寄付金控除を受ける際の留意点」などを参照)紹介してきたので割愛し、早速本題に移りたい。
ふるさと納税に関しては、これまでも返礼品の返礼割合を3割以下にすることや、返礼品を地場産品にするといった制度変更が行われてきたが、今年6月に総務省より発表された「寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集の禁止」により、ふるさと納税によるポイント還元が9月末日をもって禁止されることとなった。
まずポイント還元に関して簡単に説明すると、これまでポータルサイトを通じて寄付を行った場合、自治体からのお礼の品に加えて寄付金額に応じたポイントや特典を別途受け取ることができた。そのためポータルサイト間でポイント付与還元率を巡る競争が激化し、上記で紹介したようなふるさと納税本来の制度趣旨(詳細は総務省のホームページ参照)に沿った運用が行われていないことが問題視され、今回の決定に至った次第である。毎年12月にふるさと納税のCMや広告を見かけることは恒例であるが、今年に関しては8~9月も結構な頻度で目にしている感覚があり、その理由としては本決定に伴う駆け込み需要への期待が影響している可能性が十分考えられる。
本制度改正について、民間事業所が実施したアンケート調査によると、今回の制度変更について「反対」「残念」といった否定的な意見も数多く見られるようである。長期化する物価高によりこうしたポイントを利用して少しでも家計への負担を軽減したいと考えている方々にとっては生活への影響は避けられず、至って順当な反応であると言えよう。また、突然の制度変更にはポータルサイト側からも反対の声が挙がっており、その中には本決定の無効確認を求めて行政訴訟を起こした会社もある。ちなみにふるさと納税を巡る訴訟としては、地場産品以外の商品であるギフト券を返礼品として提供することで寄付を集めていた泉佐野市のケースが記憶に新しいが、この訴訟では同市が国に勝訴している。
最後に、以前の記事でも紹介している通り、ふるさと納税は住所地ではなく自身が希望する自治体に対して納税する制度であり、納付する住民税額が変わらないという点において節税効果はない。毎年様々な方から同じ質問を受けるので再度強調しておきたい。