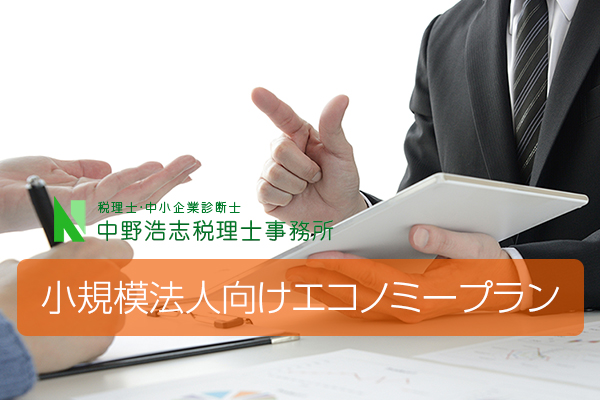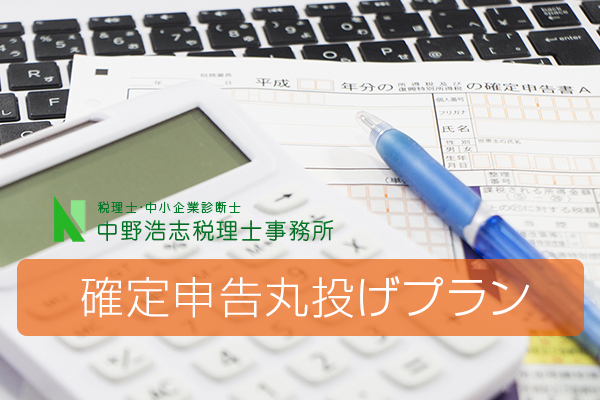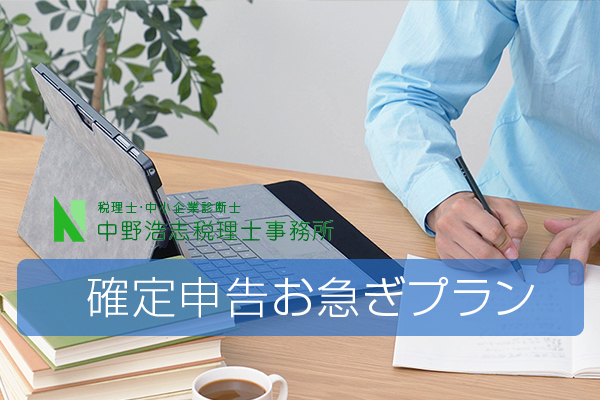厚生労働省が令和7年版労働経済白書を公表
厚生労働省はこのほど、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について統計データを活用して分析する「令和7年版労働経済の分析」(労働経済白書)を公表した。ちなみに社会保険労務士試験の一般常識系科目では、直近年の労働経済白書や厚生労働白書は最重要論点であり、私自身も各白書の概要資料にはしっかり目を通すとともに、大まかな統計数値や近年の傾向の把握にかなり時間を割いた記憶がある。
さて本題に戻り、今回の同白書では「労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて」をテーマに様々な分析が行われている。まず、雇用情勢や賃金、経済等の動きをまとめた第Ⅰ部では、2024年の労働力人口、就業者数及び雇用者数は過去最高に達するなど雇用情勢は前年に引き続き改善の動きがみられたとともに、現金給与総額は4年連続で増加し、実質賃金は一般・パートともマイナスを脱したと分析している。
続く第Ⅱ部では、労働力供給制約の下での持続的な経済成長を実現するための対応について、①労働生産性の向上に向けた課題、②社会インフラを支える職業の人材確保、③企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化に対応した雇用管理、といった観点から分析を行っている。①では、持続可能な経済成長のためには労働生産性の向上の推進が重要であり、高齢化率が高まるにつれて就業者の割合が高まる傾向のある医療・福祉業をはじめ、AIなどソフトウェア投資等による業務効率化や省力化の推進などが重要であるとしている。
次に②に関しては、人材確保には賃金をはじめとしたスキルや経験に応じた処遇の改善が必要であり、長期的に安心して働くために、スキルや経験の蓄積に応じて賃金が段階的に上昇する「キャリアラダー」と呼ばれる仕組みの構築を進めることが重要であると述べている。さらに③については、日本的雇用慣行の変化に加えてワーク・ライフ・バランスへの関心の高まりなど、雇用を取り巻く環境に様々な変化が生じている中、これに対応して企業が人材を確保するためには、賃金等の処遇改善に加えて、労働者それぞれの意識やライフイベントに合わせた働き方を可能とする柔軟な雇用管理を行うことが重要であるとしている。
なお、詳細は厚生労働省のホームページ参照。