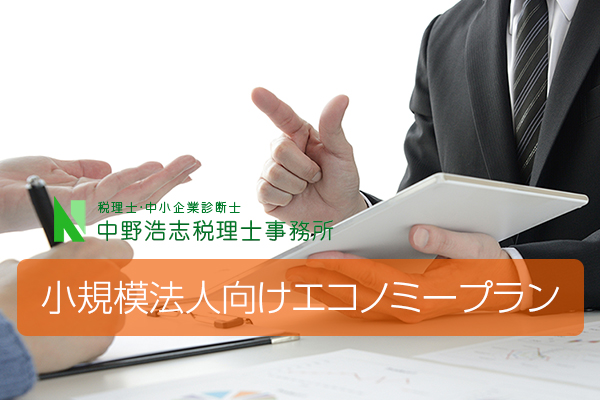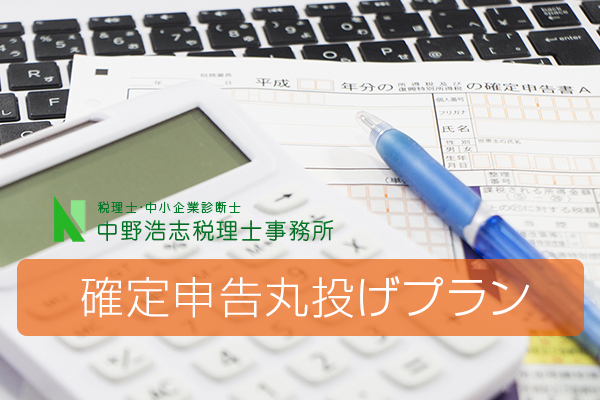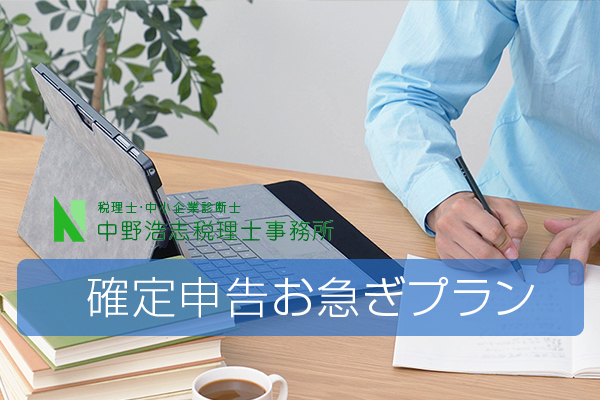相続時における消費税の納税義務の免除の特例
※本記事は令和4年9月26日時点の内容です。
今回は、以前紹介した「納税者が死亡した場合の準確定申告」などと比べると該当が限定されるケースではあるが、実務上は決して失念することのできない論点である。ちなみに、私が税理士試験の消費税法を受験した際、この論点に関する理解には大変苦労したことを今でも記憶している。加えて当時は、特殊な論点であるため実務でお目にかかることはないだろうと考えていたのだが、実際にはこれまで数回関わる機会があった。
具体的には、死亡した被相続人が個人で事業を行っていた場合において、消費税の課税事業者(死亡年の2年前における課税売上高が1千万円超)であったときは、相続で事業を引き継いだ相続人(ここでは1名と仮定)について、その相続があった日の翌日からその年の12月31日までの間の納税義務は免除されず、消費税の申告が必要となる。被相続人が負っていた納税義務をそのまま相続人が承継するという思考に基づけば、内容的には決して理解できないものではない。しかし、少なくとも一般納税者については、仮に本特例を知らなければ相続人に申告義務が生ずることに思い至る可能性は低いだろう。
次に死亡年の翌年又は翌々年について、仮に被相続人の2年前の課税売上高が1千万円以下であった場合には、事業を承継した相続人側において消費税の納税義務は生じないようにも思えるが、税法上は被相続人と相続人の2年前の課税売上高の合計額で判定することになる。例えば、被相続人の2年前の課税売上高が800万円であっても、相続人の2年前の課税売上高が500万円ある場合、その合計は1,300万円となり消費税の申告が必要となる。親子が別々に個人事業者として商売しているパターンはもとより、子はサラリーマンであり自身で商売をしていないが、事業用不動産を所有しているケースも本件に該当するので、注意が必要である。ちなみに、居住用不動産の貸付けは消費税の非課税取引(課税売上高には含めない)であり、原則として考慮不要であることから、住居のみを貸付ける小規模な不動産オーナーの多くは直接的には無関係であるかもしれない、
なお、上記特例に関連した実務的な論点については次項「相続財産が未分割である場合の納税義務の判定」で述べていきたい。また、相続で事業を引き継いだ場合の納税義務については国税庁のホームページを参照。