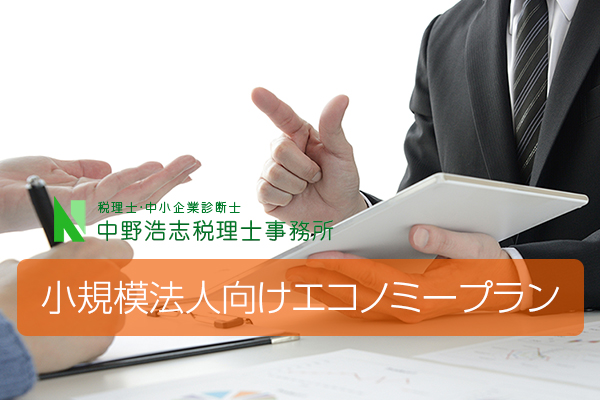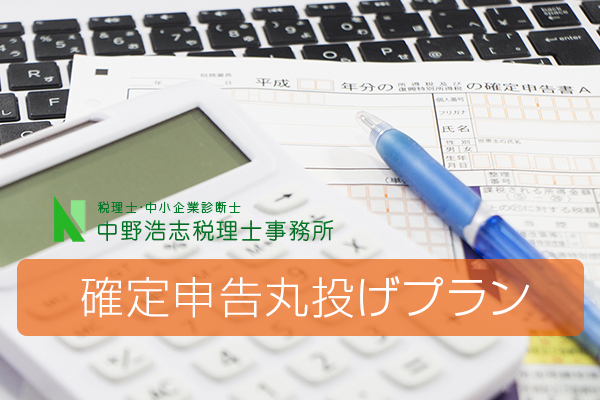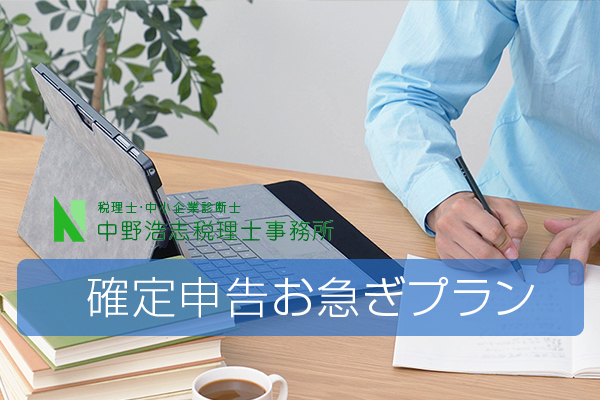税理士試験受験後の学習の進め方②
そして3つ目の考え方は、合格発表日までの期間も受験メインで時を過ごすというスタートダッシュパターンである。先行逃切り型の学習を得意とする場合には有効と考えられるが、合格したいという非常に強い意志と忍耐力が必要であるとともに、受験直前期に失速するというリスクも想定される。一方で集中力を欠かさなければ最も成果が期待できる方法であるとも考えられ、特に(あまりないケースではあると思うが)受験直後に合格を確信し、その余勢で次なる科目にチャレンジというパターンにはまると絶大な力を発揮することだろう。
最後に、過去の記事でも述べてきたように、受験勉強が実務で役に立つことは頻繁にあり、仮に何らかの理由(例:①合格していたと思って来年向けに新しい科目を学習したら不合格になってしまい、来年もその不合格科目を再受験することになった。②不合格だと思って来年向けにその不合格科目を引き続き勉強していたら、何とびっくり合格していた)によりその勉強が受験には役立たなかったとしても、実務で役立つことは十分あり得るので、受験勉強を無駄と考えてはならないという点については強調しておきたい。
私のケースで言えば、消費税法は2度不合格になり、特に受験予備校の模試で常に上位に入っていた2年目の不合格時は相当落胆したが、トータルで3年間しっかり勉強したため現在実務では得意分野になっている。また、受験4年目には法人税法・相続税法を受験し、どちらもボーダーライン上であったのでこの期間に所得税法を少し勉強したことがある。その理由は、受験した2科目のうち1科目は合格して欲しいと考え、翌年は不合格の1科目と所得税法を受験しようと考えたからである。結果は両方合格していたので、受験の観点から見れば所得税法の勉強は無駄になったわけであるが、実務では特に開業当初の段階において大いに役立った。受験段階においてはまず合格することこそが最優先であり、こうした長期的な視点にまで考えが及ばないのは当然であるし、私の受験生時代も同様であったのだが、特にこれまでの受験結果が芳しくない場合、こうした思考を頭の片隅に置くことで若干なりとも前向きな気持ちになれるかもしれない。
以上、税理士試験を終えた受験生にとって一助となれば幸いであるとともに、一人でも多くの受験生の方が合格を勝ち取られることを心より祈りたい。なお、今年の受験申込者数等の詳細については、国税庁のホームページ参照。