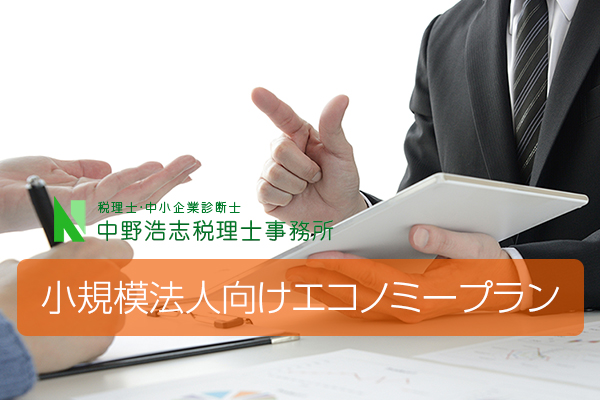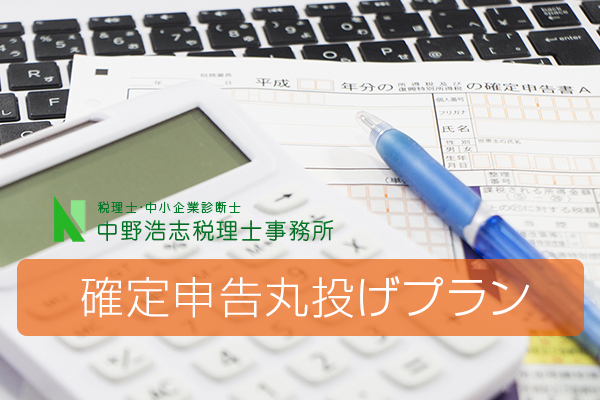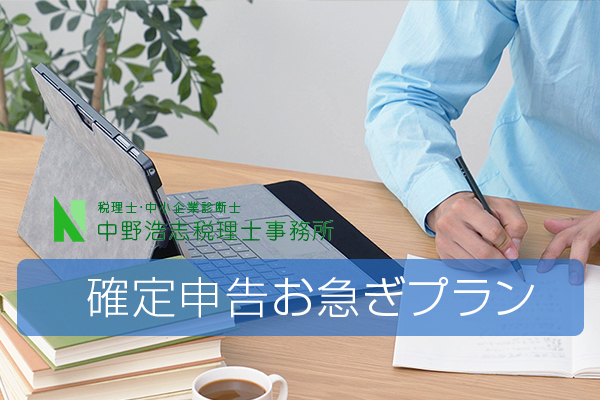就業規則の概要とその作成に当たっての留意点①
就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件、及び職場内の規律などについて定めた職場における規則集である。職場でのルールを定めた上で労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができるという点において就業規則の果たす役割は大変重要であると言える。
常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、過半数組合又は労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があるとともに、各作業所の見やすい場所への掲示・備え付け・書面の交付などによって労働者に周知しなければならない旨が法令上定められている(令和7年6月4日付け記事「従業員等の人数が常時10名以上になった場合の留意点」を参照)。なお、労働者にはパートタイム労働者やアルバイトなども含まれ、例えば閑散期に10人未満となる場合であっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合には常時10人以上の要件に該当する。
それでは、常時使用する労働者数が10人に達したことで新たに就業規則を作成する義務を有することとなった事業所は、具体的にどのように作成を進めていけば良いのか。まず参考となるのは厚生労働省がホームページに掲載しているモデル就業規則(以下「モデル」と呼ぶ)である。基本的にはこのモデルをベースとして、事業所の現状に応じて加工していけば良いとも考えられるが、担当者が労務に関する諸法令に精通していない場合、法令上記載しなければならない事項を削除したり、或いは法令上の最低基準を満たしていない内容としてしまうリスクも十分考えられる。と言うのも、就業規則は法令や労働協約に反してはならず、かつ就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項 (相対的必要記載事項)が存在するためである。
絶対的必要記載事項の例としては、①始業及び終業の時刻や休憩時間、②賃金の決定、計算及び支払の方法、③退職に関する事項、などがあり、相対的必要記載事項には①退職手当に関する事項、②安全衛生に関する事項、③職業訓練に関する事項、などが挙げられる。余談であるが採用時に明示される労働条件についても、必ず明示しないといけない事項(絶対的明示事項)と、定めの有無に応じて明示しないといけない事項(相対的明示事項)が存在し、社会保険労務士試験の労働基準法では、労働条件と就業規則の各記載事項及びその相違点を暗記することが結構大変であったと記憶している。なお、厚生労働省がホームページに掲載しているモデル就業規則については、こちらを参照。