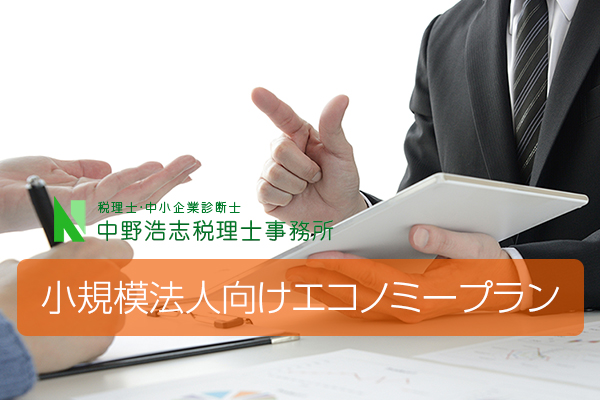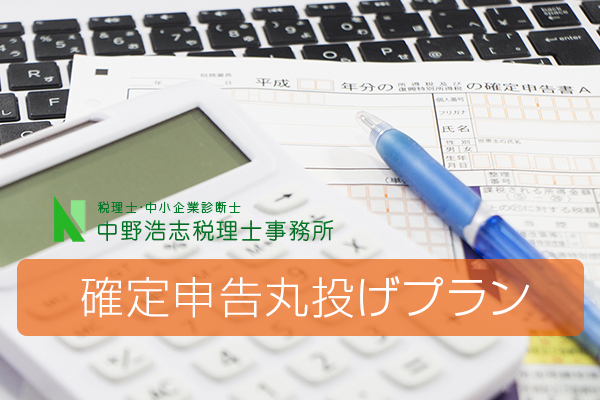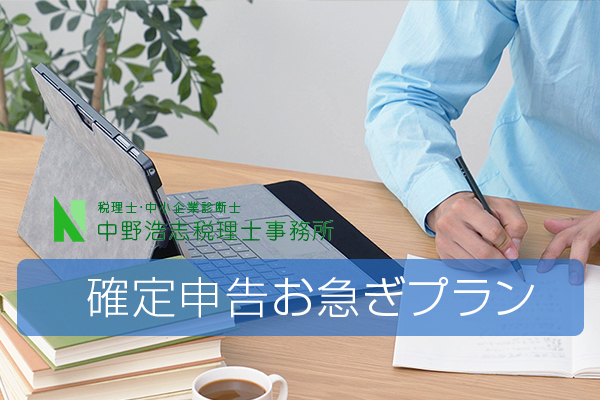国税庁が「税を考える週間」に各種イベント等を実施
国税庁では、毎年11月11日から17日までの1週間を「税を考える週間」と定め、この期間を中心に様々な広報活動やイベントなどを行っている。
税を考える週間の歴史は昭和20年代までさかのぼる。まず戦後間もない昭和22年に申告納税制度が導入され、昭和24年に国税局が発足したが、当時は税務行政に対する納税者の不満が多く聞かれていたという時代であったことから、昭和29年に「納税者の声を聞く月間」が設けられ、積極的な苦情相談、納税施設の改善及び各税法の趣旨の周知を中心とした納税思想の高揚に関する各施策を中央及び地方を通じて組織的に行うこととなった。その後幾度かの変遷を経て、平成16年からは単に税を知るだけでなく能動的に税の仕組みや目的を考えてもらい、国の基本となる税に対する理解を深めてもらうことを明確にするため現在の名称に変更されている。
今年の税を考える週間では、「これからの社会に向かって」をテーマとして、国民に日常生活と税の関わりを理解してもらうことにより納税意識の向上を図ることとしており、期間中には①新聞やインターネット広告などのマスメディアを通じた広報、②主に大学生や社会人を対象とした、国税局や税務署による講演会・説明会の開催、③全国の中学生・高校生から応募のあった税に関する作文の入選作品の表彰、などが行われる。また、国税庁のホームページでは、同庁の職場の魅力や仕事をドラマ仕立てで紹介した動画や、インターネットを利用した手続きに関する動画などを掲載している他、クイズやゲーム・アニメなどを通じて税について学ぶ税の学習コーナーや、学校での授業や家庭での学習で活用できる税の仕組みに関する学習コンテンツの公開など、非常に多彩なメニューで構成されている。
長期化する物価高により、国民の税に関する関心はこれまで以上に高まっているものと考えられ、こうした取り組みを通じて納税者の税に関する知識や理解を深めていくことはこれまで以上に重要となっている。併せて、今後物価高対策として打ち出されるであろう様々な施策についても、納税者にとってシンプルかつ実効性のある制度にして欲しいところである。なお、詳細は国税庁のホームページを参照。