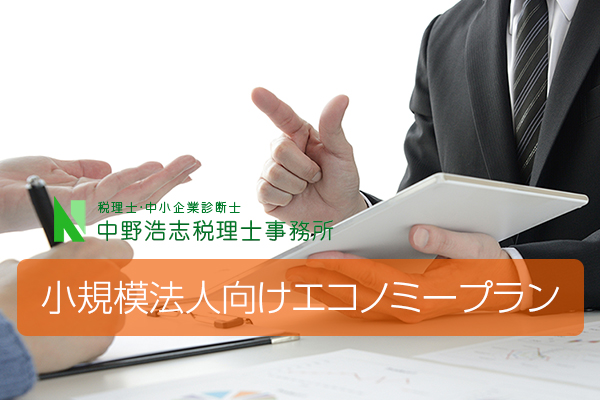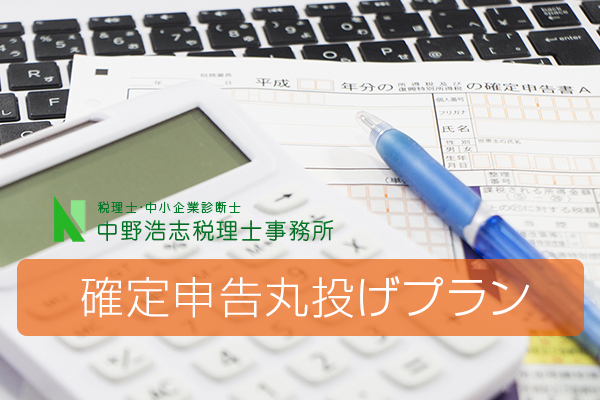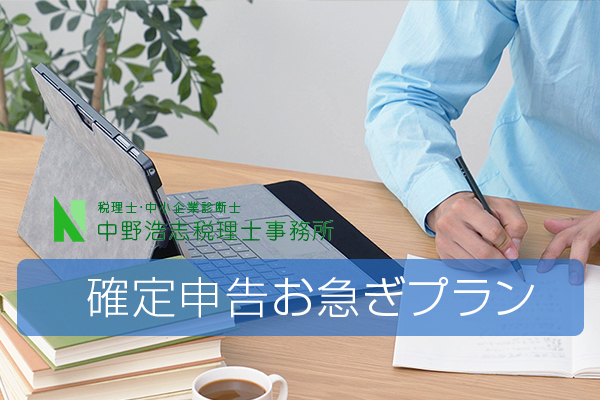総務省が高齢者の人口や就業状況などを公表
総務省はこのほど、敬老の日(9月15日)を迎えるに当たり、統計からみた我が国の高齢者のすがたについて取りまとめた。
まず、65歳以上人口は3,619万人と前年に比べて5万人減少している一方、総人口に占める割合は29.4%と過去最高を占めており、その割合は人口4千万人以上の世界38か国の中では最も高い。10人当たり3人が高齢者という事実を統計数値で改めて確認するに及び、少子高齢化の流れが益々加速していることを実感せざるをえない。
また、国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、この割合は今後も上昇を続け、私のような第2次ベビーブーム期(1971年~1974年)に生まれた世代が65歳以上となる2040年には34.8%、 2050年には37.1%になると見込まれている。さらに年齢階層別では、後期高齢者に該当する75歳以上人口が2,124万人と前年に比べて49万人増加しており、全体に占める割合も17.2%を占めている点も注目される。ちなみに、私が社会保険労務士試験の受験生であった頃は、人口の5人に1人が75歳以上となる2025年問題が大きくクローズアップされていた。
次に65歳以上の就業者数は、21年連続で増加して930万人と過去最多となり、就業者総数に占める65歳以上の就業者の割合についても13.7%と過去最高に達した。私の日常生活の中にあっても、高齢と思しき配送ドライバーや交通整理員などを見かけるケースは一昔前と比べて明らかに増加しており、この結果は至って順当と言える。また、日本の65歳以上の就業率は25.7%であり、主要国との比較においても高い水準にある点は十分予想できた一方、韓国が日本よりも遥かに高い割合(38.2%)である点は意外であった。高齢者が働きやすい就労環境の整備が図られているのか、或いは公的年金等の支給額だけでは生活できないためやむなく就労しているのかなど理由は色々考えられるが、主要国の中でも突出しているため個人的には大変興味を持った。
さらに、65歳以上の就業者を産業別に見ると、「卸売業・小売業」「医療・福祉」「サービス業(他に分類されないもの)」の順に多く、特に「医療・福祉」の就業者数は10年前と比べて約2.3倍増加して115万人に達している。この理由としては、やはり医療や介護の現場における慢性的な人手不足などが大きく影響しているものと考えられる。
なお、詳細は総務省のホームページ参照。